「社会人になったら本を読む時間がない」
そんな声をよく耳にします。確かに、仕事に追われる毎日の中で、読書の優先順位は下がりがちです。しかし、20代のうちに読書の習慣を身につけておくと、30代になった時に他の人たちとの差が歴然に現れます。
今回は、新社会人や20代におすすめの書籍を10冊をお伝えします。
- 読書をする理由がわからない方
- どんな本を読もうか悩んでいる方
- 20代で成長をしたい方
なぜ20代の読書が重要な理由
20代は、社会人としての基礎を形成する重要な時期です。この時期の読書には、以下のような意義があります。
- 視野の拡大
社会人になると、どうしても自分の仕事の範囲に視野が限定されがちです。
読書は、異なる視点や考え方に触れる貴重な機会を提供してくれます。 - 先人の知恵を効率的に習得
誰もが経験する悩みや課題に対して、すでに多くの先人が解決策を見出しています。
それらの知恵を本から学ぶことで、無駄な回り道を避けることができます。 - 自己投資としての価値
20代は自己投資の10年間です。
1冊3,000円程度の本には、著者の何十年もの経験と叡智が詰まっています。
これほど費用対効果の高い自己投資はありません。
よく同じジャンルの書籍は数冊以上読みなさいと言われています。
それは、同じジャンルの書籍であっても違うことが書かれているだけでなく、
まったく同じことが書かれています。
全く同じことはそのジャンルにおいて本質のことで、違うことは著者が取った行動によるものです。
こういったヒントが書籍には沢山書かれているので、読書の習慣は何歳になってもおすすめな理由です。
この記事で紹介する本の選定基準
世の中にはおすすめの沢山の書籍があります。
しかし、全てを紹介することはできないので、この記事で紹介する10冊は、以下の基準で厳選しました。
ただし、これらの本は一度読んで終わりではありません。
何度も読み返し、その時々の状況に応じて新たな気づきを得られる本ばかりです。
では、さっそく具体的な書籍の紹介に移っていきましょう。
おすすめ書籍①『7つの習慣』スティーブン・R・コヴィー
有名な書籍なので、大学生の時に読んだことがある方もいるかもしれません。
社会人で読書週間のある方に聞くと、必ずこの1冊の名前はあがるはずです。
それだけ、長年愛されてきた書籍でもあります。
本書の核心
人生とキャリアの成功に不可欠な7つの習慣を、具体的な実践方法とともに説く世界的ベストセラー書籍です。
単なるノウハウ本ではなく、「人生の原則」「物事の本質」を扱う一冊です。
なぜ20代で読むべきか
社会人としての心構えと行動指針を確立する20代。
この時期に本書を読むことで、以後の人生における意思決定の軸を形成することができます。
本書から学べる重要ポイント
- 主体的な生き方(第1の習慣)
- 「反応する」のではなく「行動を選択する」という考え方
- 具体例:困難な職場状況でも、自分にできることから始める姿勢
- 実践ポイント:日々の出来事に対する自分の反応を観察する習慣づけ
- 目的を持った行動(第2の習慣)
- 人生の最終目標から逆算して今すべきことを考える
- ミッションステートメントの作成方法
- 実践ポイント:5年後の理想像を書き出し、そこから現在やるべきことを導き出す
- 優先順位の設定(第3の習慣)
- 重要かつ緊急でないタスクに時間を使う重要性
- タイムマネジメントの具体的方法
- 実践ポイント:週間計画の立て方と優先順位マトリックスの活用法
読んだ後の行動プラン
- 自分の価値観を書き出す
- 週間計画表の作成を始める
- 重要/緊急マトリックスでタスクを整理する
書籍情報
| 著者 | スティーブン・R・コヴィー |
| ページ数 | 450ページ |
| 読破目安時間 | 2週間程度 |
| おすすめの読み方 | 章ごとに実践期間を設けながら読み進める |
| 関連図書 | 『完訳7つの習慣』 『7つの習慣コヴィー博士の集中講義シリーズ』 |
| 著者について | スティーブン・R・コヴィーは、リーダーシップの研究者であり、コンサルタント。世界中の企業や組織でリーダーシップ研修を行い、数々の賞を受賞しています。 |
おすすめ書籍②『嫌われる勇気』岸見一郎・古賀史健
日本人は自殺者数が多いことで知られています。
関係ないと思われがちですが、人間関係が大きな原因だと言われています。
そんあ人間関係を見直すためのヒントが書かれているのがこの書籍になります。
職場の上司や同僚との人間関係に悩んでいる方におすすめの書籍です。
本書の核心
アドラー心理学をわかりやすく解説した対話形式の本です。
「他者の評価に振り回されない生き方」を説き、特に新社会人が陥りやすい「承認欲求」の罠から抜け出す方法を示唆します。
なぜ20代で読むべきか
社会人になって初めて直面する様々な人間関係の悩み。
上司や同僚との関係、仕事での評価など、他者の目を特に意識しやすい時期だからこそ、この本から学ぶべき視点があります。
本書から学べる重要ポイント
- 「課題の分離」という考え方
- 自分の課題と他者の課題を明確に区別する
- 具体例:同僚の仕事の質は相手の課題であり、自分がコントロールすべきではない
- 実践ポイント:日々の悩みが「自分の課題」なのか「他者の課題」なのか整理する
- 「承認欲求」からの解放
- 他者からの評価に依存しない自己受容の方法
- 人に嫌われることを恐れない勇気の持ち方
- 実践ポイント:自分の行動の動機が「誰かに認められたいから」になっていないか確認する
- 「貢献感」という人生の目的
- 競争ではなく協調の視点
- 共同体感覚の育て方
- 実践ポイント:毎日の仕事で「誰かの役に立てたこと」を記録する
読んだ後の行動プラン
- 自分の行動の動機を見直す
- 「課題の分離」ワークシートの作成
- 毎日の「貢献ノート」をつける
書籍情報
| 著者 | 岸見一郎 |
| ページ数 | 294ページ |
| 読破目安時間 | 1週間程度 |
| おすすめの読み方 | 対話形式なので、登場人物の疑問に自分を重ねながら読む |
| 関連図書 | 『幸せになる勇気』 『アドラー心理学入門』 |
| 著者について | 岸見一郎はアドラー心理学の第一人者。古賀史健はノンフィクションライター。二人の共著により、難解な心理学の概念を身近な対話形式で伝えることに成功しています。 |
実践的な活用法
- 職場での活用
- 上司からの評価を過度に気にしない
- チーム内での建設的な意見の出し方
- 同僚との健全な距離感の保ち方
- プライベートでの活用
- 友人関係での過度な気遣いからの解放
- SNSでの「いいね」に振り回されない心構え
- 自己決定の基準を持つ
おすすめ書籍③『君たちはどう生きるか』吉野源三郎
この書籍は1937年に書かれた書籍ですが、現代社会だからこと読んでほしい一冊です。
ジブリで映画化もされて有名になった書籍の一つです。
あなたに合った、人生の生き方や働き方を見つけるヒントになるはずです。
本を読み慣れていない方にはマンガ版もあり、読みやすい一冊ですよ。
本書の核心
1937年に書かれた本ですが、現代社会でこそ読むべき普遍的な価値を持つ作品です。
主人公のコペル君が叔父さんとの対話を通じて、人としての生き方や社会との関わり方を学んでいく過程を描いています。
なぜ20代で読むべきか
社会人になって初めて「働く」という経験をする中で、「なぜ働くのか」「社会で生きるとは何か」という根本的な問いに直面します。
本書は、そんな問いに向き合うための重要な視点を提供してくれます。
本書から学べる重要ポイント
- 「考える力」の養成
- 当たり前だと思っていることを疑問視する姿勢
- 物事の本質を見抜く観察力
- 実践ポイント:日常の些細な出来事から社会の仕組みを考える習慣をつける
- 社会との関わり方
- 個人と社会の関係性の理解
- 働くことの意義を考える
- 実践ポイント:自分の仕事が社会にどうつながっているか図示してみる
- 生きる姿勢の確立
- 正直に生きることの意味
- 他者への思いやりと自分の信念を持つこと
- 実践ポイント:日々の判断に迷った時の「軸」を作る
読んだ後の行動プラン
- 「考えるノート」の作成(コペル君のように)
- 毎日の仕事の社会的意義を考える時間を持つ
- 自分なりの「生き方の指針」をまとめる
職場での具体的な活用法
- 日常業務での活用
- 単純作業にも意味を見出す視点
- 顧客や同僚との関係性の捉え方
- 組織の中での自分の役割の理解
- キャリア形成での活用
- 長期的な視点での仕事の選び方
- スキルアップの方向性の決め方
- 働く目的の明確化
書籍情報
| 著者 | 吉野源三郎 |
| ページ数 | 398ページ |
| 読破目安時間 | 2週間程度 |
| おすすめの読み方 | 一章ずつ自分の経験と照らし合わせながら、じっくり読む |
| 関連図書 | 『君たちはどう生きるか』集中講義 こう読めば100倍おもしろい』 |
| 著者について | 吉野源三郎は、ジャーナリスト・思想家。本書は息子に向けて書いた教科書として構想されましたが、世代を超えて読み継がれる名著となっています。 |
印象的な場面と現代での解釈
- 雨の中の行列の場面
- 集団心理の理解
- 現代のSNSでの同調現象との類似性
- 真理を追究する場面
- データや情報に振り回されない本質的な思考の重要性
- 現代のファクトチェックの必要性
おすすめ書籍④『バビロン大富豪の教え』大橋弘祐
富を築くための原則をこの書籍で学ぶことができます。
原則を学ぶことで今後の人生の軸になってくれる書籍の一つです。
また、バビロン大富豪の教えもマンガ版と書籍版があります。
本書の核心
古代バビロニアを舞台に、富を築くための普遍的な原則を物語形式で解説した古典『バビロンの大富豪』を、現代のビジネスパーソン向けに解説した一冊です。
お金との向き合い方、資産形成の基本原則を、具体的かつ実践的に学ぶことができます。
なぜ20代で読むべきか
初任給を手にし、自身のお金の管理を始める20代。
この時期にお金との正しい付き合い方を学ぶことで、将来の経済的自由への基礎を築くことができます。
本書から学べる重要ポイント
- 収入の使い方の原則
- 「収入の10分の1は自分のもの」という黄金則
- 給与からの自動的な貯蓄の仕組み作り
- 実践ポイント:給与日に自動振替の設定をする
- 堅実な資産形成の考え方
- 複利の力を理解する
- 長期投資の重要性
- 実践ポイント:つみたてNISAなどの活用方法を理解する
- 借金との付き合い方
- 「良い借金」と「悪い借金」の区別
- クレジットカードの賢い使い方
- 実践ポイント:毎月の支出を項目別に管理する
実践的な活用プラン
- 収支管理の基本
- 家計簿アプリの活用方法
- 固定費の見直し
- 変動費のコントロール方法
- 投資の始め方
- リスク許容度の確認
- 分散投資の実践
- 定期的な投資計画の立て方
お金の管理の具体例
- 月収30万円の場合の配分例
- 生活費:50%
- 固定費:30%
- 貯蓄・投資:10%
- 自己投資:5%
- 娯楽費:5%
- 年間の資産形成計画
- つみたてNISA:月2万円
- 財形貯蓄:月1万円
- 緊急用預金:月2万円
書籍情報
| 著者 | スティーブン・R・コヴィー |
| ページ数 | 240ページ |
| 読破目安時間 | 1週間程度 |
| おすすめの読み方 | 各章の終わりにある実践ワークを必ず行う |
| 関連図書 | 『学校では教えてくれないお金の授業』 『10歳から知っておきたいお金の心得〜大切なのは、稼ぎ方・使い方・考え方』 |
| 著者について | 大橋弘祐は、ファイナンシャルプランナーとして多くの若手社会人の資産形成をサポート。難しい金融の概念を分かりやすく説明することに定評があります。 |
特に重要な教訓
- 「収入以下の生活」の習慣化
- 「支出は必要なものから」の原則
- 「借金は収入を生むためだけに」の鉄則
- 「長期的な視点」での資産形成
このように、単なる投資や節約の技術だけでなく、お金に対する基本的な考え方や姿勢を学ぶことができる一冊です。特に20代のうちにこれらの原則を身につけることで、将来の経済的な選択肢を広げることができます。
おすすめ書籍⑤『お金の大学』両学長
お金について学びたいならこの一冊は読みやすくておすすめです。
読書する時間がないというかたでもすぐに読み終わるので読書が苦手な方にも読みやすい一冊です。
本書の核心
『お金の大学』は、お金に関する基本的な知識を「貯める」「稼ぐ」「増やす」「守る」「使う」の5つの項目に分けて解説する書籍です。
複雑になりがちなマネーリテラシーを初心者にも分かりやすく、実践的な方法で学べる内容となっています。
お金の不安から解放され、人生を豊かにするための具体的なステップを提案しています。
なぜ20代で読むべきか
お金の扱い方を学ぶことは早いほど良いです。
特に20代は収入が増え始める一方で、生活費や趣味に支出が増える時期。
この本を通じて、お金を無駄にせず、将来の資産を形成する方法を知ることで、経済的な自由への一歩を踏み出せます。
本書から学べる重要ポイント
- 「貯める」:無駄遣いを防ぐ仕組み作り
- 固定費削減の具体的な方法
- 家計簿アプリの活用
- 実践ポイント:通信費や保険料を見直し、毎月の固定費を最低限にする
- 「稼ぐ」:本業+副業で収入アップ
- 副業の始め方やリスク管理
- 自分の強みを活かす稼ぎ方
- 実践ポイント:月5万円を目指して副業を計画する
- 「増やす」:資産運用の基本を学ぶ
- インデックス投資やつみたてNISAの活用
- リスクを抑えた長期投資戦略
- 実践ポイント:毎月少額から積立投資をスタート
- 「守る」:無駄な損失を防ぐ
- 保険や詐欺への正しい対処法
- 老後資金を守る方法
- 実践ポイント:必要な保険を選び、無駄な契約を解約する
- 「使う」:お金で幸福度を上げる方法
- 自分や家族の成長に投資する
- 感謝や経験にお金を使う意義
- 実践ポイント:日々の生活で「幸せに直結する出費」を意識する
実践的な活用法
- 固定費削減の実施
- 家賃交渉、プラン変更での通信費節約
- 支払い明細を確認し、無駄をカット
- 投資の第一歩
- つみたてNISAの口座を開設
- 初めての投資先を選び、小額から始める
- 副業のプランニング
- 自分の趣味やスキルを収益化する方法を検討
- YouTubeやブログ運営のスタートガイドを活用
具体的な実践例
- 毎月の支出を確認
- 固定費と変動費を明確に分ける
- 家計簿アプリで支出管理を始める
- お金の勉強習慣を作る
- 本書を読み返しながら、YouTubeやブログで知識を深める
- 投資や副業について週1回調べる
書籍情報
| 著者 | 両学長 |
| ページ数 | 272ページ |
| 読破目安時間 | 1週間程度 |
| おすすめの読み方 | 1つの項目ごとに行動リストを作り、即実践する |
| 関連図書 | 『バビロンの大富豪』 『お金は寝かせて増やしなさい』 |
| 著者について | 両学長は、リベラルアーツ大学の創設者。お金や人生に役立つ情報を提供するYouTuberで、多くのファンを持つ。 |
特に印象的な教え
- 「貯めたお金が未来の自由を作る」
- 「お金は働かせて増やすもの」
- 「自分への投資こそ最大のリターン」
- 「固定費削減は最強の貯金方法」
本書の魅力は、初心者でも取り組みやすい具体的なアドバイスと、長期的な視野での資産形成を教えてくれる点です。
特に、収入が限られている20代にとって、効率よくお金を管理し、増やす方法が手に取るように分かります。
おすすめ書籍⑥『給与明細から読み解くお金のしくみ』高橋創
社会人にとって大切な税金について学ぶことができます。
会社に勤めていると確定申告を行うことはないかもしれませんが教養としてしっかりと20代のうちに学んでおくことが大切です。
『給与明細から読み解くお金のしくみ』高橋創
本書の核心
給与明細に隠された「お金のしくみ」を紐解きながら、税金、社会保険、手取り収入についてわかりやすく解説する一冊です。
普段あまり意識しない給与明細の項目に目を向けることで、労働の対価として得るお金がどのように分配され、運用されているかが理解できます。
特に、節税や効率的な資産形成の方法についても具体的なアドバイスが書かれており、知識を実生活に活かせる内容が豊富です。
なぜ20代〜30代で読むべきか
社会人として働き始めた20代や、ライフイベントが増える30代は、自分のお金について知識を深める絶好の時期です。
給与明細を読み解く力を身につけることで、将来の資産形成や生活の安定性を高めることができます。また、「知らないと損する」情報が満載なので、若いうちに習得することで大きな差を生む可能性があります。
本書から学べる重要ポイント
- 給与明細の基本構造
- 基本給、控除項目、手取りの関係性を理解する
- 各項目が何に使われているのかを知る
- 実践ポイント:自分の給与明細を見直し、項目ごとに理解を深める
- 税金の仕組み
- 所得税、住民税の計算方法とその仕組み
- 節税のポイントと活用できる控除
- 実践ポイント:確定申告やふるさと納税で節税を試してみる
- 社会保険の重要性
- 健康保険や年金がどのように機能しているか
- 社会保険料が高額である理由とその価値
- 実践ポイント:将来受け取れる年金額をチェックし、資産計画に活かす
- 資産形成とライフプラン
- 貯蓄、投資、節税のバランスの取り方
- 積立NISAやiDeCoなどの制度の有効活用
- 実践ポイント:自分の手取り額から無理のない投資計画を立てる
- 「お金の流れ」を知ることの重要性
- 稼いだお金が社会にどう還元されているかを把握
- 消費者としての選択が経済に与える影響を理解
- 実践ポイント:支出を見直し、節約や寄付を通じてお金の使い方を最適化する
実践的な活用法
- 給与明細の「見える化」
- 給与明細をExcelなどに入力し、各項目の割合を可視化する
- 節税を考慮したライフプランニング
- 住宅ローン控除や教育資金控除を活用し、家計の負担を軽減する
- 社会保険料の負担軽減策
- 退職や転職時における健康保険や年金の選択肢を検討
具体的な実践例
- 控除額の最適化
- 年末調整や確定申告を活用して、還付金を最大化
- 貯蓄型保険や投資信託の選択
- 手取り収入の一部を長期的な資産形成に振り分ける
- 生活コストの見直し
- 必要な支出と不要な支出を仕分けし、固定費を削減
書籍情報
| 著者 | 高橋創 |
| ページ数 | 224ページ |
| 読破目安時間 | 3〜4時間 |
| おすすめの読み方 | 1章ごとに自分の給与明細を確認し、内容を実生活に落とし込む |
| 関連図書 | 『お金の大学』 『新版正しい家計管理 正しい家計管理長期プラン編』 |
| 著者について | 税理士として活動し、一般の人にもわかりやすいお金の解説書を執筆。 特に税金や保険に関する教育的な著作が多い。 |
特に印象的な教え
- 「お金の仕組みを知ることで、選べる未来が広がる」
- 「税金は敵ではなく、味方につけるべきもの」
- 「給与明細を読み解く力が、人生の安定を支える」
本書は、「給与明細を見るのが面倒」と思っていた人でも、興味を持って読み進められる構成です。
お金に対する理解を深め、日常生活の中で具体的な改善を行いたいと考える人にとって必読の一冊です。
おすすめ書籍⑦『Think clearly』新井紀子
本書の核心
『Think Clearly』は、思考をクリアにし、より良い決断を下すための52の思考法則を紹介する一冊です。
人間が陥りがちな認知バイアスや思考の罠をわかりやすく解説し、それを克服するための実践的なアプローチを提供しています。
シンプルな行動や視点の転換によって、より理性的で賢い選択が可能になることを説いています。
なぜ20代〜30代で読むべきか
20代〜30代は、人生の大きな決断を多く迫られる時期です。
進学、就職、結婚、転職、資産形成など、重要な選択をする際に、冷静でクリアな思考を持つことは成功へのカギとなります。
本書は、感情に左右されず、長期的な視点で行動を選ぶ力を養うための指南書として最適です。
本書から学べる重要ポイント
- 認知バイアスを見抜く力
- 「確証バイアス」や「アンカリング効果」に気づき、冷静に判断する
- 実践ポイント:複数の情報源からバランスの取れた情報収集を行う
- 「決めない」ことの重要性
- 重要な決断ほど即断しない
- 実践ポイント:選択肢を一晩寝かせ、感情が冷めた状態で考える
- 長期的な視点の育成
- 短期的な快楽ではなく、長期的な成果に注目する
- 実践ポイント:目先の利益ではなく、10年後の自分にとって価値のある選択を意識
- 過剰な情報の排除
- 情報過多が判断力を鈍らせる危険性を理解する
- 実践ポイント:情報源を限定し、自分にとって必要な情報だけを選択
- 成功者の思考パターンを取り入れる
- 「成功した人」の背後にある偶然や見えない要素を考慮する
- 実践ポイント:他者の成功体験を参考にする際は、背景の違いを冷静に分析
実践的な活用法
- 意思決定の改善
- 過去の選択を振り返り、バイアスが影響した箇所を特定する
- 仕事での効率向上
- 情報整理や優先順位の設定に思考法を応用する
- 人間関係の強化
- 感情に左右されず、理性的なコミュニケーションを心がける
具体的な実践例
- 選択肢の削減
- 毎朝の服選びをルーティン化し、重要な意思決定にリソースを集中
- To-Doリストの精査
- 今日やるべきことと、やらなくてもいいことを明確に分ける
- 「ノイズ」を排除する生活
- SNSの使用時間を制限し、情報収集の質を向上
補足情報
| 著者 | ロルフ・ドベリ |
| ページ数 | 384ページ |
| 読破目安時間 | 1週間程度 |
| おすすめの読み方 | 気になる章から読み始め、実生活に取り入れる |
| 関連図書 | 『Think Smart』 『習慣が10割』 |
| 著者について | ロルフ・ドベリは、ベストセラー作家であり、思想家。複雑な現代社会で必要な思考法やライフスタイルの提案を行うことを得意としています。 |
特に印象的な教え
- 「感情に左右されないことが、最も賢い選択をする近道である」
- 「情報は多ければ多いほど良いわけではない」
- 「真の成功は、偶然と努力のバランスで成り立っている」
本書は、日常生活の中で「思考のノイズ」を減らし、冷静で的確な判断を可能にする具体的なガイドブックです。
特に、仕事や人間関係で思い悩む人にとって、大きなヒントを与えてくれる一冊です。
おすすめ書籍⑧『超効率勉強法』メンタリストDaiGo
この書籍は、多く出回っているので、古本屋で¥500程度で沢山売られています。
そのため、とりあえず購入して読んでみる本としてはおすすめです。
本書の核心
『超効率勉強法』は、膨大な量の勉強を短時間で効果的に吸収する方法を解説した一冊です。
科学的根拠に基づき、効率よく知識を習得し、記憶に定着させるメソッドを紹介。
DaiGo氏自身の経験と心理学の知見を掛け合わせた実践的な内容が魅力です。
なぜ20代で読むべきか
20代は、キャリア形成や資格取得、自己成長に積極的に取り組む時期です。
本書の内容を活用することで、忙しい毎日の中でも効率的に学びの時間を確保し、成果を上げる方法を身に付けることができます。
本書から学べる重要ポイント
- 「記憶力を最大化する」方法
- 短期記憶を長期記憶に変えるテクニック
- 実践ポイント:復習のタイミングを計画的に設定する(例:1日後、1週間後)
- 「集中力を高める」環境作り
- 作業効率を上げる環境の整え方
- 実践ポイント:ポモドーロ・テクニック(25分集中+5分休憩)を試す
- 「効率的なインプット・アウトプット」
- 知識を頭に入れるだけでなく、活用する学習法
- 実践ポイント:学んだ内容を人に説明することで理解を深める
- 「科学的に裏付けられた学習法」
- マインドマップやアクティブリコールの活用
- 実践ポイント:授業やセミナーを聞いた後に自分で要点をまとめ直す
- 「モチベーションを維持する」技術
- 勉強を習慣化し、やる気に頼らない仕組み作り
- 実践ポイント:目標を小分けにし、達成感を得やすくする
実践的な活用法
- 資格試験の勉強
- 暗記科目の復習頻度を計画的に設定
- 過去問を繰り返し解くことで実践力を強化
- スキルアップの学習
- 新しいスキルを学ぶ際、学んだ内容を小さなプロジェクトに活用
- 学習中に意識的にアウトプットを取り入れる
- 日常生活での学び
- 読書内容を要約し、SNSやブログでシェア
- 興味を持った分野について1日1つ調べてメモを残す
具体的な実践例
- 記憶を定着させるための復習スケジュール
- 学習した日、翌日、1週間後、1ヶ月後に再確認する
- ポモドーロ・テクニックの導入
- スマホのタイマーを使い、25分間集中して勉強+5分休憩を繰り返す
- 学んだ内容を話す練習
- 学習内容を友人や家族に説明し、フィードバックをもらう
書籍情報
| 著者 | メンタリストDaiGo |
| ページ数 | 248ページ |
| 読破目安時間 | 2〜3日(実践を含む場合は1週間程度) |
| おすすめの読み方 | 1章ずつ読み進め、気になったテクニックを試してから次に進む |
| 関連図書 | 『自分を操る超集中力』(メンタリストDaiGo) 『アウトプット大全』(樺沢紫苑) |
| 著者について | メンタリストDaiGoは心理学をベースに、人間の行動や思考を科学的に解析するメンタリスト。 ビジネスや勉強術に関する数多くの著書を持つ。 |
特に印象的な教え
- 「勉強とは技術であり、努力ではない」
- 「記憶力は訓練次第で誰でも伸ばせる」
- 「学ぶときはインプットだけでなくアウトプットが鍵」
- 「勉強効率を上げるには、環境と習慣が最も重要」
本書は、「ただがむしゃらに勉強する」時代から「科学的に効率よく学ぶ」時代への転換を示唆する一冊です。
短時間で成果を出したい方には特におすすめです。
おすすめ書籍⑨『イシューからはじめよ』安宅 和人
本書の核心
『イシューからはじめよ』は、成果を最大化するための「問題解決力」を養う方法を解説したビジネス書です。
膨大なタスクや情報に振り回されるのではなく、本当に解くべき「イシュー(課題)」を見極める力を鍛え、効率よく価値を生み出すアプローチを提示します。
特にビジネスや学術研究、プロジェクトマネジメントに役立つ内容です。
なぜ20代で読むべきか
20代は、キャリアのスタート地点で多くの仕事や学びの選択肢に直面する時期です。
本書を読むことで、重要な課題に集中する力を身に付け、成果を出すための基盤を築けます。
「何に時間を使うべきか」を迷わず判断できるようになる点が20代に特に有益です。
本書から学べる重要ポイント
- 「イシュー」の定義と見極め方
- イシューとは「答えを出すべき問い」
- 価値が高く、答えが出せる問いを優先する重要性
- 実践ポイント:作業に取りかかる前に「これは価値あるイシューか?」と問う
- 「仮説思考」の活用
- 初めから完璧を求めるのではなく、仮説を立てながら進める
- 実践ポイント:目標に向かう途中で検証・修正を繰り返すプロセスを取り入れる
- 「集中と選択」の技術
- 限られた時間とリソースを、インパクトのある仕事に集中させる
- 実践ポイント:TODOリストを見直し、重要でないタスクを大胆に削除
- 「アウトプットの質を高める」方法
- 結果を明確にイメージし、そこに到達するプロセスを逆算する
- 実践ポイント:ゴールを「具体的な結果」で定義し直す
- 「仮説検証を加速させる」データ活用術
- データをただ集めるのではなく、必要な情報を迅速に収集する
- 実践ポイント:データ収集の目的を事前に明確にして効率化
実践的な活用法
- ビジネスでの活用
- 企画提案時に「本当に解決すべき課題」を絞り込む
- チームでのプロジェクトを進める際に優先順位を明確化
- 個人の学習・成長
- 資格試験やスキルアップの学習計画に「本当に必要な学び」を取り入れる
- 目標達成のために不要な作業を削ぎ落とす
- 日常生活での応用
- 日々のTODOリストから重要事項だけを選択する
- 無駄な会議や情報収集の時間を削減
具体的な実践例
- タスクの洗い出しと優先順位付け
- 毎朝、その日のタスクを列挙し、「重要なイシューか?」を基準に振り分ける
- 仮説を立てたプロジェクトの進行
- 新しいプロジェクトを始める前に、解決すべき課題と想定する結果を仮説として設定
- 効率的なデータ収集
- 必要なデータを具体的に定義し、検索範囲を絞って時間短縮
| 著者 | 安宅和人 |
| ページ数 | 240ページ |
| 読破目安時間 | 一週間程度 |
| おすすめの読み方 | 各章ごとに書かれているポイントを日常のタスクにすぐ応用してみる |
| 関連図書 | 『ゼロ秒思考』 『エッセンシャル思考』 |
| 著者について | 安宅和人はマッキンゼーでのコンサル経験を経て、ヤフー株式会社CSO(チーフストラテジーオフィサー)を務める。データサイエンスやビジネス戦略の第一人者。 |
特に印象的な教え
- 「すべての仕事には本質的なイシューがある」
- 「量よりも質が問われる時代において、何を解くべきかを見極める力が重要」
- 「優れたアウトプットは優れたイシューから生まれる」
本書は、ただ頑張るのではなく、「考え方」そのものを変えることで、成果を最大化する方法を具体的に示しています。特にビジネスパーソンやリーダーには必読の内容です。
おすすめ書籍⑩『幸せになる勇気』岸見一郎・古賀史健
幸せになる勇気は嫌われる勇気と同じ著者が書いている書籍です。
書籍の形的に好き嫌いはあるかもしれませんが、幸せとはなんなのかとこのブログのコンセプトでもある、『豊かな人生』とは何なのか?をよく知れる書籍ですよ。
本書の核心
『嫌われる勇気』の続編として、アドラー心理学の「幸福論」に焦点を当てた対話形式の本です。
「幸せ」は既に自分の中にあり、それを妨げているのは自分自身の思い込みだという視点から、具体的な幸せへの道筋を示しています。
なぜ20代で読むべきか
社会人として歩み始めた時期に、「成功」や「幸せ」の定義を自分なりに確立することは重要です。
周りとの比較や社会的な価値観に振り回されがちな20代だからこそ、本質的な幸福について考える機会が必要です。
考えるためのヒントが載っているのが、この書籍でもあります。
本書から学べる重要ポイント
- 「人生は共同体の中にある」という視点
- 他者との関わりの中での幸福の見つけ方
- 競争ではなく協力の意識
- 実践ポイント:毎日の人との関わりを「貢献」の視点で振り返る
- 「課題の分離」の深い理解
- 他者の不幸は他者の課題である
- 過度な親切が相手の成長を妨げる可能性
- 実践ポイント:人間関係での「手出しし過ぎ」をチェックする
- 「いま、ここ」での生き方
- 過去や未来ではなく現在に焦点を当てる
- 目標達成後の幸せではなく、今の幸せを見つける
- 実践ポイント:毎日、今の生活での「小さな幸せ」を記録する
実践的な活用法
- 仕事での活用
- 成功の定義の見直し
- 同僚との健全な関係構築
- 仕事への意味付けの変更
- プライベートでの活用
- 人間関係の整理
- 生活習慣の改善
- 自己受容の実践
具体的な実践例
- 毎日の振り返り
- 誰かの役に立てたこと
- 感謝できること
- 自分で決断したこと
- 幸福度を高める習慣
- 朝の感謝の習慣
- 共同体への参加
- 自己決定の機会を増やす
書籍情報
| 著者 | 岸見一郎・古賀史健 |
| ページ数 | 288ページ |
| 読破目安時間 | 1週間程度 |
| おすすめの読み方 | 各章の終わりで自分の生活への適用を考える |
| 関連書籍 | 『嫌われる勇気』 『アドラー心理学入門』 |
| 著者について | 岸見一郎:アドラー心理学の第一人者 古賀史健:ベストセラー作家、ノンフィクションライター |
特に印象的な教え
- 「幸せは選択である」という考え方
- 「承認欲求からの解放」の重要性
- 「人生の意味は自分で見つける」という視点
- 「変えられないものを受け入れる」勇気
本書の特徴は、難しい心理学の概念を日常的な対話を通じて理解できるように工夫されている点です。特に、20代の若手社会人が直面しやすい悩みや課題に対して、具体的な解決の視点を提供してくれます。
まとめ
今回は20代に読んでほしい書籍10冊をご紹介しました。
これらの書籍は基本的な『豊かな人生』のヒントが詰まっています。
どの書籍もどの時代においても役にたつ知識なので、一度は読んでみてくださいね。
AmazonのKindle unlimitedに登録すれば500万冊以上の書籍を月額¥980で読むことができるのでこれから読書週間を身につけたい方は、おすすめですのでぜひ登録して活用しましょう!
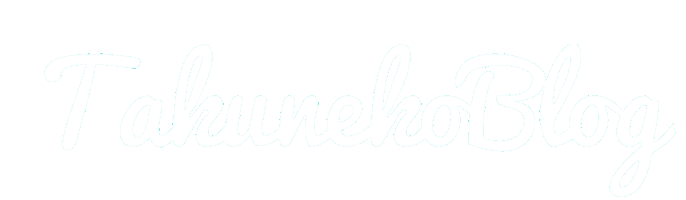



コメント